ご質問はこちらへ
質問用フォーラムです。ご質問の前に質問のしかたをご覧ください。
- 匿 名 の投稿
Appendix のリスト追加
- Yoshihiro TANAKA の投稿
2点質問させて下さい。
AppendixをTable of Contents に下記のようにAppendixの開始ページのみ表示させるにはどうすればよいでしょうか?
Appendixのリストを下記のように図や表と同じように追加するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
Table of Contents
Chap1......................1
Chap2......................10
Chap3......................20
Appendix...................30
List of Figure
Fig1.......................4
Fig2.......................7
List of Table
Tab1.......................10
List of Appendices
App1.......................30
App2.......................40
appendixパッケージを使ってみましたがうまくいきませんでした。
"List of Appendices"の文字列を表示することはできましたが、肝心の中身をつくることができませんでした。listoffiguresみたいにしてAppendixも追加できないでしょうか?
AppendixをTable of Contents に下記のようにAppendixの開始ページのみ表示させるにはどうすればよいでしょうか?
Appendixのリストを下記のように図や表と同じように追加するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
Table of Contents
Chap1......................1
Chap2......................10
Chap3......................20
Appendix...................30
List of Figure
Fig1.......................4
Fig2.......................7
List of Table
Tab1.......................10
List of Appendices
App1.......................30
App2.......................40
appendixパッケージを使ってみましたがうまくいきませんでした。
"List of Appendices"の文字列を表示することはできましたが、肝心の中身をつくることができませんでした。listoffiguresみたいにしてAppendixも追加できないでしょうか?
このトピックを読む
(現在の返信数: 5)
Gsview 4.9 の設定について
- switch case の投稿
Windows VISTA SP2 x64, Win32TeX(阿部さんのインストーラから)gs9.0
gsview4.9 32bit
Win32TeX を10/8に入れ替えたのですが、gsview からの印刷におかしな
線が出て困っております。色々検索してみたのですが同じ症状の報告なり
正しい設定なりを見つけられずギブアップです。添付しましたのがその画像
です。同じdviファイルから dvipdfmx でも dviout からでも問題無く印刷出
来ています。現在、作成した全ての tex ファイルから同様な症状が出ていま
す。私は、どこを間違えているのでしょうか。よろしくお願い致します。まだ、
暫く ps ファイルから印刷したいのです。
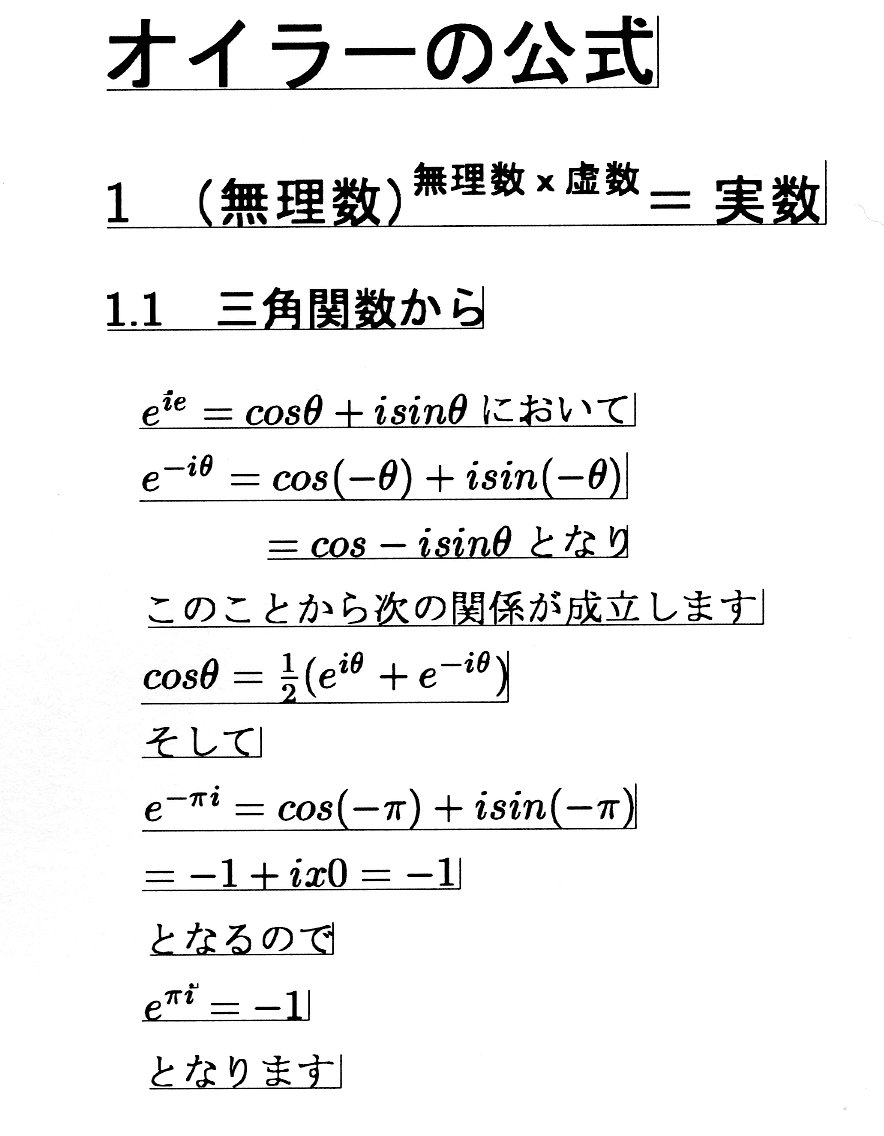
このトピックを読む
(現在の返信数: 6)
Adobe-Japan1-5全文字を出力した際右へのはみ出し
- DUYA AYUD の投稿
otfが使えるようになったのでAdobe-Japan1-5全文字を奥村先生の美文書作成入門のように出力してみようと思いlongtable環境を用いて50個ずつ横に並べたところ、ところどころ謎の空白が入り表の右へはみ出てしまいました。しかし特にOverfullなどのエラーは出ないので原因がわかりません。
自分の出力したPDFでは9700,9750,12050の段が横に飛び出ております。
またdvipdfmxを実行するときに** WARNING ** CMap has higher supplement number than CIDFont: Ryumin-Light
** WARNING ** Some chracters may not be displayed or printed.
と出はしてますが自分では今回の件には無関係と判断しております。
原因がお分かりになる方は教えてください。
自分の出力したPDFでは9700,9750,12050の段が横に飛び出ております。
またdvipdfmxを実行するときに** WARNING ** CMap has higher supplement number than CIDFont: Ryumin-Light
** WARNING ** Some chracters may not be displayed or printed.
と出はしてますが自分では今回の件には無関係と判断しております。
原因がお分かりになる方は教えてください。
このトピックを読む
(現在の返信数: 3)
索引の作成について
- TeX userの人 の投稿
今年の4月に奥村先生の美文書作成入門第4版のCDROMからインストールしました。
先日、TeXで文章を打っていました。その際、初めて索引をつけてみようと思い、
プリアンプル部分に
\usepackage{makeidx}
\makeindex
と打ち、
三角関数\index{さんかくかんすう@三角関数}
などと複数の索引に掲載したい語を入れ、
\printindex
と最後(\end{document})の手前に打って、Winshellでコンパイルしました。
しかし、索引が作成されておらず、更には
foo.idx
という拡張子のファイルが作成されていませんでした。
どのようにすれば索引が出力されるようになるのでしょうか
このトピックを読む
(現在の返信数: 13)
pdfの紙面サイズをA5にしたい
- 天羽 優子 の投稿
奥村先生の最新版の本からインストールして使っています。TeXShopの設定も本の通りにしています。
\documentclass[a5j,twocolumn,10pt,notitlepage,openany,twoside]……
とやったファイルをコンパイルすると、できたpdfファイルでは紙面サイズA4のままで、A5の範囲にだけ出力されます。
これまでは、コンパイル後に
--AppleScript
try
set cmd to "/usr/local/texlive/p2009/bin/i386-apple-darwin10.3.0/dvipdfmx -p a5 -o " & #PDFPATH# & " " & #DVIPATH#
do shell script cmd
on error
display dialog "Some error occured."
end try
とやって、A5サイズに変換していました。
ところが、このスクリプトを使う方方では、includegraphicsで取り込んだeps画像ファイルの含まれるページが白紙になってしまいます。A4サイズで最初にできた時は画像が入っているのですが、変換すると白紙になります。
何とか、画像が入ったまま、紙面サイズをA5で出す方法は無いでしょうか。
\documentclass[a5j,twocolumn,10pt,notitlepage,openany,twoside]……
とやったファイルをコンパイルすると、できたpdfファイルでは紙面サイズA4のままで、A5の範囲にだけ出力されます。
これまでは、コンパイル後に
--AppleScript
try
set cmd to "/usr/local/texlive/p2009/bin/i386-apple-darwin10.3.0/dvipdfmx -p a5 -o " & #PDFPATH# & " " & #DVIPATH#
do shell script cmd
on error
display dialog "Some error occured."
end try
とやって、A5サイズに変換していました。
ところが、このスクリプトを使う方方では、includegraphicsで取り込んだeps画像ファイルの含まれるページが白紙になってしまいます。A4サイズで最初にできた時は画像が入っているのですが、変換すると白紙になります。
何とか、画像が入ったまま、紙面サイズをA5で出す方法は無いでしょうか。
このトピックを読む
(現在の返信数: 2)
beamer 3.10について
- じゃっかん さん の投稿
MacOS 10.6.4
小川さんのサイト
(http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/herogw/)より,
Drag & Drop pTeXをダウンロードしてから
インストールし,geometryをupgrade
beamerを3.10にupgrade
pdf,xcolorもupgradeしました.
%----ex.tex
¥documentclass[dvipdfm]{beamer}
¥title{テスト}
¥author{hoge}
¥date{2010.10.29}
¥begin{document}
¥frame{¥titlepage}
¥begin{frame}
¥frametitle{ひとつめ}
あいうえお
¥end{frame}
¥end{document}
%----------
をTeXShopにてコンパイルすると,
No file ex.nav.
! Undefined control sequence.
¥beamer@frameslide ...duration=}¥thispdfpagelabel
{¥insertframenumber } ¥xde...
l.10 ¥frame{¥titlepage}
?
とエラーメッセージがでます.
何がだめなのでしょうか?
小川さんのサイト
(http://www2.kumagaku.ac.jp/teacher/herogw/)より,
Drag & Drop pTeXをダウンロードしてから
インストールし,geometryをupgrade
beamerを3.10にupgrade
pdf,xcolorもupgradeしました.
%----ex.tex
¥documentclass[dvipdfm]{beamer}
¥title{テスト}
¥author{hoge}
¥date{2010.10.29}
¥begin{document}
¥frame{¥titlepage}
¥begin{frame}
¥frametitle{ひとつめ}
あいうえお
¥end{frame}
¥end{document}
%----------
をTeXShopにてコンパイルすると,
No file ex.nav.
! Undefined control sequence.
¥beamer@frameslide ...duration=}¥thispdfpagelabel
{¥insertframenumber } ¥xde...
l.10 ¥frame{¥titlepage}
?
とエラーメッセージがでます.
何がだめなのでしょうか?
このトピックを読む
(現在の返信数: 2)
texshopを使用してのpdfの図の挿入について
- hiki shima の投稿
[改訂第5版]LaTeX2e美文書作成入門を購入し、付属のCDでLaTeXをインストールして使用しています。
texshopを使用してpdfの図を挿入する際、Use "-V" switch to change output PDF versionという注意が出て挿入できなかったのでLaTeX2e美文書作成入門を読んだところ、pdfのバージョンが、1.5であるために挿入できないことがわかりました。
対処法として、dvipdfmxに-V 5というオプションをつけて起動すると書いてあるのですが、これはどこに書けばいいのでしょうか?
texshopで¥usepackage[dvipdfmx,hiresbb]{graphicx}を¥usepackage[dvipdfmx-V 5,hiresbb]{graphicx}のようにしてみましたがダメでした。
申し訳ありませんがどなたかご教示お願いいたします。
texshopを使用してpdfの図を挿入する際、Use "-V" switch to change output PDF versionという注意が出て挿入できなかったのでLaTeX2e美文書作成入門を読んだところ、pdfのバージョンが、1.5であるために挿入できないことがわかりました。
対処法として、dvipdfmxに-V 5というオプションをつけて起動すると書いてあるのですが、これはどこに書けばいいのでしょうか?
texshopで¥usepackage[dvipdfmx,hiresbb]{graphicx}を¥usepackage[dvipdfmx-V 5,hiresbb]{graphicx}のようにしてみましたがダメでした。
申し訳ありませんがどなたかご教示お願いいたします。
このトピックを読む
(現在の返信数: 2)
TeXユーザの集い 2010 開催予定 (10/23土@東大生研)
- KUROKI Yusuke の投稿
昨年は「TeXユーザの集い 2009」を盛況のうちに開催できまして,ありがとうございました.
今年はどうしようかと検討してまいりましたが,「TeXユーザの集い 2010」を開催しましょうということになりました.日程は昨年と少しずらして 10/23(土) を,場所は昨年と同じく東京大学生産技術研究所 (駒場IIキャンパス) を予定しています.
公式ページは http://oku.edu.mie-u.ac.jp/texconf10/ にあります.
中身についてはいろいろ計画中です.決まり次第,随時公式ページにてお知らせします.
今年はどうしようかと検討してまいりましたが,「TeXユーザの集い 2010」を開催しましょうということになりました.日程は昨年と少しずらして 10/23(土) を,場所は昨年と同じく東京大学生産技術研究所 (駒場IIキャンパス) を予定しています.
公式ページは http://oku.edu.mie-u.ac.jp/texconf10/ にあります.
中身についてはいろいろ計画中です.決まり次第,随時公式ページにてお知らせします.
このトピックを読む
(現在の返信数: 8)