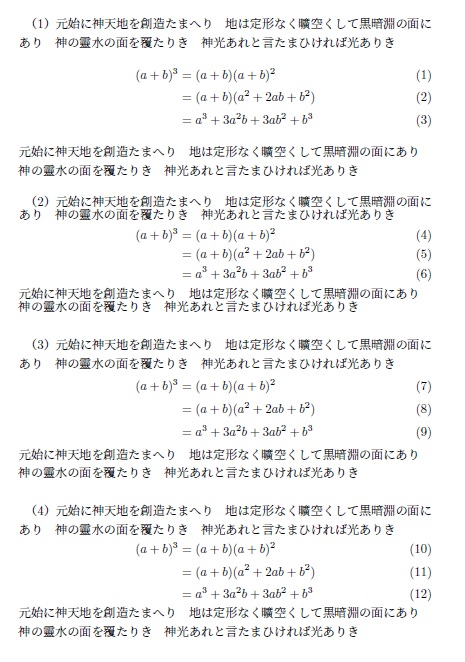お世話になります。北川です。
最近、別行立て数式の前後について考えており、参考書のように調整したいと思いました。『大学への数学』(東京書籍)をみると、数式の上下のスペースは、通常のテキストの行間と等しいことが分かりました。ここで、「行間」とは\baselineskipのことではなく、ある行とその次の行に和文字の隙間(\baselineskip-1\zhに相当?)のことです。
また、alignの上下やalign中の各数式の上下のスペースも同様でした。
テキスト中の数式に分数やインテグラルを用いた場合は、「行間」が挿入されていることが分かりました。
そこで、各パラメータを次のように設定しました。
\setlength{\lineskip}{\baselineskip-1\zw}
\setlength{\lineskiplimit}{3pt}
\AtBeginDocument{
\abovedisplayskip=0\abovedisplayskip
\abovedisplayshortskip=0\abovedisplayshortskip
\belowdisplayskip=0\belowdisplayskip
\belowdisplayshortskip=0\belowdisplayshortskip
\setlength{\jot}{0pt}
}
これは、別行立ての数式の上下を0ptにして、ほぼ強制的にlineskipを入れることを意図したものです。
しかし、alignの前後及び各数式の上下のスペースは想定よりも大きくなりました。
そこで、先の目的を達成するためには、どのように各パラメータを調整すればよいか、ご教授いただければ幸いです。
LuaLaTeX + jlreqで組んでいます。
よろしくお願いいたします。